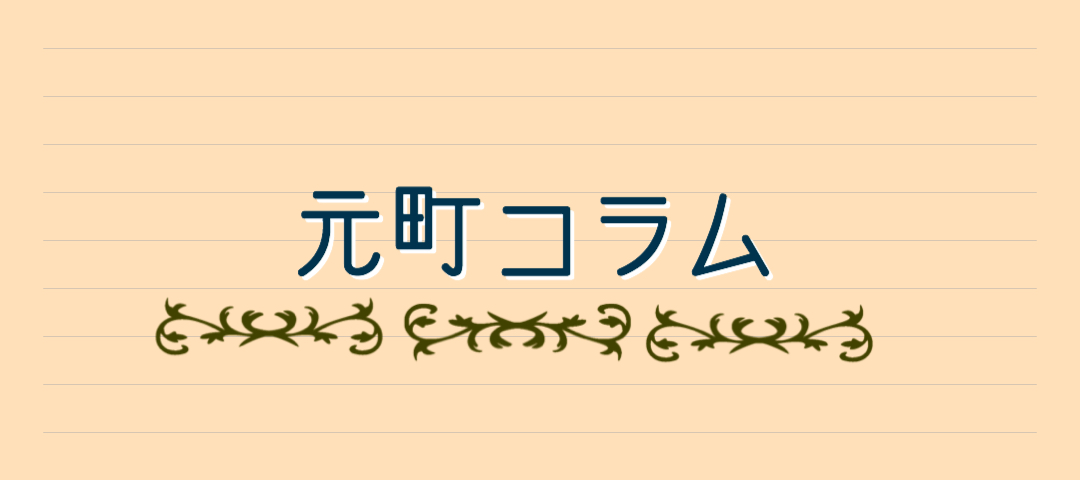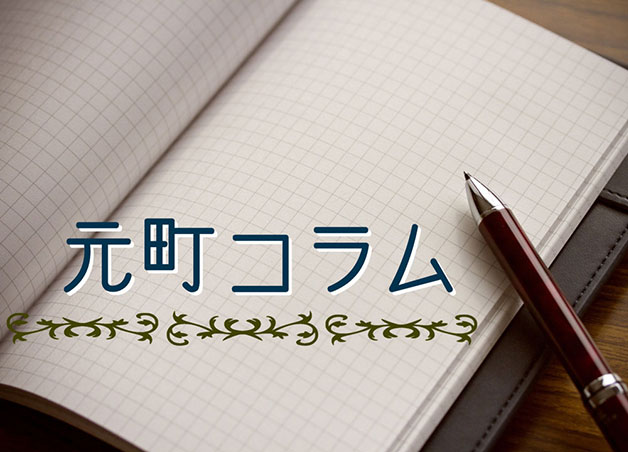*本コンテンツは、これまで元町公式メールマガジンにて配信しておりましたコラムです。
2021年(令和3年)1月5日号 元町コラム
横浜開港200年〜Y200(2059年)を夢みて!
【特集】 行く川の流れは絶えずして、、、その41
〜高島嘉右衛門さんの事 その(18) 〜
謹んで新春のお慶びを申し上げます。
本年もどうぞよろしくお願い致します。
いつもとは少々異質な今年のお正月の三が日でしたが、皆さま、いかがお過ごしでしたでしょうか? 初詣や年賀状、おせち料理といったお正月恒例の風習や伝統行事は、嘉兵衛(後の高島嘉右衛門)が生まれ育った江戸時代末期には、まだ存在していませんでした。
意外に思われるかも知れませんが、初詣が正月行事として一般化したのは明治中期から大正中期にかけての事で、一応、江戸時代にもお正月に神社仏閣に参拝する風習があるにはありましたが、それは自分の住まう家から、その年の恵方(年神様がいる方角のこと)にある社寺に参拝する「恵方詣り」でした。恵方は年によって変わりますので、毎年参拝する社寺が異なっていたという事になります。

※晴れ着姿で恵方詣りを楽しむ粋な男衆。
縁起物がたくさんぶら下がった飾り物を担いでいますので、
お参りの後の帰り道なのかも知れません。
(三代歌川豊国 作、『春曙恵方詣』の一部分)
「恵方詣り」はやがて恵方とは関係のない「初詣」へと変化して現在に至りますが、それは、どうやら鉄道の発達という時代の変遷に関係があったように思われますので、今後、機会を得て調べてみたいと思います。
さて、現代のおせち料理もお正月の定番ですが、このおせちのスタイルが一般化したのは昭和も戦後になってからのことでした。庶民の生活も落ち着き、百貨店が見栄えのある三段重のおせちを売り出したことが発端ですが、もともと「おせち料理」は、奈良時代、季節の節目(節句)に宮中で行われた「節会(せちえ)」という宴会で供された料理「御節供(おせちく)」が略されたものといわれています。ですので、節句の祝膳はすべて「おせち料理」だったわけで、その節句のなかでもお正月が一番重要であったことから、「おせち料理=お正月の祝膳」となって現在に至った事が記録に残されています。
その一方で、江戸時代にもおせち料理に似たお正月の祝い膳が存在しており、それは「食積(くいつみ)」(関西では「蓬莱(ほうらい)」)と呼ばれ、年神様へのお供え物として飾るだけのもので、実際に食する料理ではありませんでした。

※学業成就、商売繁盛の神様として人気の「元町厳島神社」。
密を避けながら、、安心安全の元町初詣でお会い致しましょう。
思うに、文化とは移りゆく世相の変遷によって生まれ出ずるものですが、この元町コラムもホームページ(元町メルマガ)の発足と共にスタートし、おかげさまで、このお正月で「18年目」を迎えるに至りました。元来はご登録頂いた会員の皆様に、毎月、5日と20日に自動配信でお届けしていましたが、昨今は一般公開されて、気楽にお読み頂けるコーナーになっております。お正月の風物の起源を新年のご挨拶代わりに述べながら、特集としての高島嘉右衛門さんに焦点をあてて、そろそろ本題へと話を進めさせて頂くことに致しましょう。
前号までをおさらいしておくと、、、、
1832年12月24日(天保3年11月3日)、父、遠州屋嘉兵衛(本姓・薬師寺)、母、「くに」の姉弟6子の長男として江戸三十間堀(現・東京都中央区銀座)で生まれた高島嘉右衛門(幼名・清三郎、後に嘉兵衛から嘉右衛門に改名、号は呑象)は、後年、鉄道敷設の為の横浜港の埋め立てをはじめとする種々の横浜の発展に寄与して「横浜の父」、また、吉田勘兵衛や苅部清兵衛らとともに「横浜三名士」とも呼ばれて、「高島町」(横浜市西区)という地名にその名を残す程の「横濱の恩人」である事から、ご縁のあった横濱元町として、その栄誉を讃える意味で種々の資料をまとめて、ここにその記録をお届けしている次第です。
幼少のころは父の教えに従い、四書五経や六諭衍義(Rikuyu-Engi=寺子屋の教科書)などを学び、14歳で父の営む材木商兼普請請負業や盛岡藩製鉄事業に従事して、父や弟と共に東北の鉱山開発事業で7年間の重労働に挑むものの、父の死後、困窮武士の救済法令である棄捐令(Kien-Rei)による債権の放棄や債務繰り延べによる損害に加えて次姉の養子の放蕩による莫大な借金の存在が判明し、その返済に奔走します。
22歳の時に材木商を始めた嘉兵衛(後の高島嘉右衛門)は、安政の大地震による江戸の大火で被害を受けた佐賀藩江戸屋敷の普請や、買い占めた材木の売却によって2万両(現代の20億円)の大きな利益を得るものの、盛岡藩江戸屋敷普請の際、全財産を投資した材木の大暴風雨による流出などで、逆に2万両の負債を抱えるに至ります。
借金返済に苦労し行き詰っている折に、縁あった佐賀(鍋島)藩家老・田中善右衛門の斡旋により、1859年(安政6年)、横濱に伊万里焼の磁器や白蝋を一手に扱う肥前屋を開店。その折に外国人を相手に、国内外の金銀による交換差益の旨味を耳にすると、法で禁じられていた小判(金)の売買に手を出し、その儲けから借金は完済出来たものの、取り締まり方に追われて身を隠す事態となって、後に奉行所に自首。その罪で、伝馬町入牢が1860年(万延元年)、嘉兵衛、28歳の時でした。
5年後の1865年(慶応元年)、33歳の年に放免され、その折に「高島嘉右衛門」と改名する事によって、いよいよ横濱と本格的に関わる事になるわけですが、現在の当コラムの場面は、まだ、地獄の伝馬町牢屋敷から牢替えになった浅草溜の二番牢の中、副牢名主の囚人・嘉兵衛(後の高島嘉右衛門)が遭遇した大惨事の真っ最中です。
副牢名主と言っても囚人には変わりがない嘉兵衛なわけですが、首謀者の脱獄騒ぎから大暴動に発展した阿鼻叫喚の一夜が明けようとしていた牢内は、真っ暗闇な中、うめき声も絶えて物音ひとつしない不気味な静寂に包まれていました。
外を取り囲んでいるのは、応援に駆けつけた南町奉行所の役人達ですが、誰一人、気味悪がって牢の中に入って検死検分をしようとはせず、囚人名簿をくくりながら、格子越しに一人ずつ囚人の名前を大声で読み上げてはいるものの、その点呼に答えたのは百数十人居た囚人の中で嘉兵衛ただ一人でした。
しかも、隠れていた高天井の籠の中からヌーッと嘉兵衛が顔を出したので、驚いた皆は、一瞬、幽霊かと騒めき、牢を取り囲んでいた役人の輪もウワッと広がりました。その籠は、湿気の多い牢生活の工夫で、病原ともなるカビ類を防止する意味からシーズンオフの衣料を取りまとめて保管しておく為の大きな籠でした。
嘉兵衛が通称・道成寺と呼ばれていたその籠に隠れる発想を得たのは、暴動が起き、銃が乱射され出した瞬間の事で、それは暗示から得た閃(hirame)きによるもので、それは、脱獄の首謀者達に脅迫的に依頼された占いの際に、時間稼ぎの目的で行なった本格占いによって得られた「卦」(ka)に由来していました。
嘉兵衛は、自ら導き出した「卦」が暗示する意味を暴動の瞬間も考えていたわけですが、それは、奇妙にも自らがかつて得た「水風井」の卦と同じだったことから、30年前、「万両分限(何万両もの財産を持つ富豪のこと)になれるが人災によって命を縮めることになる」との浅草の老易者、三枝師の言葉を思い出すと同時に、「生死の危機に直面したらできるだけ高いところに逃げろ」との暗示の記憶が蘇り、とっさに頭上に大籠が吊り下げられている事に気がつくや、「これだ!」とばかりに素早い行動に移ることが出来たのです。
嘉兵衛が牢内で占った「水風井 三爻」(すいふうせい さんこう)の卦は、井戸の水が未だ汲みあげられることもなく使用されてもいない状況を意味していて、上の方に近くなるほど水質も良くなるものの、水脈には的中している井戸ながら、水そのものを使ってくれる人がそれに気付いていないという、井戸、つまり水という命の源泉が確保されていることと、上にあればあるほど全てが清らかで安全という暗示だったのでした。
嘉兵衛が暗い牢内で、暴徒の発生を告げる非常召集の早鐘の音を耳にして、「鐘? 鐘…そうだ!道成寺だ!」と直感的に閃くや、上を見上げた瞬間は、まさに卦の暗示の真の意味を理解した瞬間でもあったのです。
 ※舞台 京鹿の子娘道成寺の一場面より。
※舞台 京鹿の子娘道成寺の一場面より。
道成寺(Doh jyo ji)というのは、安珍清姫の伝説に基づいて作られた能の『道成寺』のことで芝居の人気演目ですが、女人禁制の掟を破って訪れてきた白拍子花子が、舞を披露していると、鐘が大音響とともに地に落ち、花子は落ちて来たその鐘に閉じ込められます。僧侶らが必死でこの鐘を引き上げると花子は蛇体に変じていたという物語ですが、その、通称「道成寺」が牢にもある事に嘉兵衛は閃いたのでした。
牢の天井に吊り下げられている籠の通称が「道成寺」なら、その籠を上げ下ろしする綱の動きこそ、井戸水を汲み上げる釣瓶(Tsuru be)そのものですから、これが卦の「水風井」にドンピシャリだったのですから、占い恐るべしです。
役人の発砲や、囚人同士の殺戮(Satsu riku) の大混乱の中、嘉兵衛は畳が10数枚重ねられている一番高い牢名主の畳座によじ登ると、天井の羽目板に飛びつき、猿のような手さばきで道成寺の中に潜り込むと、息を潜めて朝を待ったのでした。
脱獄騒動の首謀者の一人、権之助が、死に際に最後の力を振り絞って襲いかかり、深傷(fukade)を負った嘉兵衛が我に返った場所は役人達の詰所でした。包帯が厚く巻かれた右腕には鋭い痛みが走るものの「牢内の唯一人の生き残り」と役人に告げられた嘉兵衛は、重い身を起こすと、西方浄土の神仏に向かって、深く深く合掌するのでした。
(続く、、、)
Tommy T. Ishiyama