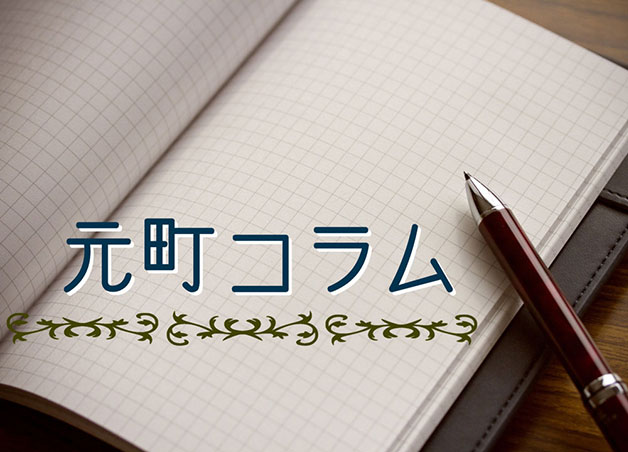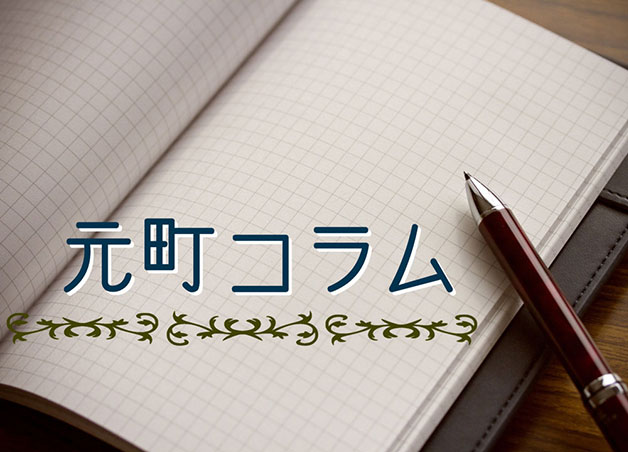*本コンテンツは、これまで元町公式メールマガジンにて配信しておりましたコラムです。
2020年(令和2年)7月20日号 元町コラム
横浜開港200年〜Y200(2059年)を夢みて!
【特集】 行く川の流れは絶えずして、、、その30
〜高島嘉右衛門さんの事 その(7) 〜
令和2年7月現在、コロナ禍(COVID-19)の急襲によって世界を席巻していた恐怖の集団催眠から目覚めた様に日本プロ野球が開幕し、元町も2月以来延期になっていた恒例のチャーミングセールが開催されるなど、平常を取り戻す為の全力投球が開始されています。

※ある日の「かえもん公園」近影。別邸跡地。
京急・神奈川駅、東急・反町から徒歩6分。
横浜駅西口の繁華街の北側を通る旧東海道沿いにある。
当時は一面の海(野毛の浦)の向こうに居留地が眺めら
れたが、現在はご近所の皆さんの小さな憩いの場だ。

※「高島山公園」。高島嘉右衛門晩年の住居跡。
そこから「高島山」と呼ばれるようになり、
この公園の名に由来している。

※高島山公園内にある「望欽台」(Bou Kin Dai)
望欣台の碑は明治10年建立の高島嘉右衛門を顕彰する碑。
嘉右衛門は、高島学校などの洋学校の創設・経営や瓦斯事業、
高島町埋立てなどの土木事業のほか、洋館の建築、
港座(洋式劇場)の経営など多方面に貢献しました。
港内の繁栄と事業の功績を望み、ひとり欣然として
心を癒したことから、この高島台の高台は望欣台と呼ばれる。
現在は高島山公園にあるこの碑はもとは近くの高島邸にあった。

さて、幾多の災難を乗り越えてビジネスに邁進し、大きな信用を更に獲得した父・嘉兵衛に同行して、清三郎(高島嘉右衛門)もご縁を頂くことになる奥州南部藩や佐賀鍋島藩の江戸屋敷を訪れ出したのは14歳の頃でした。
また、しばしば普請の現場を訪れる清三郎は棟梁や大工の会話に耳を澄ませて、誰かれとなく質問をするのが常で、そんな清三郎を目を細めて眺めている嘉兵衛は、彼の質問のレベルが確実に上向いてくる事に非凡な物を見いだし、満足そうな微笑みで見守るのでした。
そんな清三郎が興味を抱いたのは、鍋島藩の家臣・力武弥右衛門(Rikitake Yaemon)の話で、それは長崎の出島で、唯一、貿易を許されていたオランダ商館の幹部達から鍋島藩が得ていた世界の最新情報の数々でした。
まだまだ、幕末の実感も無いペリー来航以前の江戸、そんな町の真ん中から世界に目を開こうとしている清三郎は、まるで誰かに選ばれた人物の様相を呈しており、入ってくる知識を素直に吸収して行き、、地球が丸いこと、海の向こうには多くの国々がありそれらは遥かに進んだ文明を有していること、黒船という甲鉄艦があって、石炭という地中から掘り出した燃える石を動力として世界の海を航海していること、そして、外国人は皆、背と鼻が高く色白で青い目をしており、彼らが使いこなしている銃器と大砲の火力は優れており、その数量が国力の差となっていることなどなど、、貪るように聞き入る清三郎の目は一層輝きを増すのでした。
そんなある日、清三郎が父・嘉兵衛に呼ばれて奥座敷に行くと、いつになく真剣な眼差しで鍋島藩江戸屋敷の普請を命じられます。ある確信を清三郎に抱いた嘉兵衛の英断は、南部藩邸の奥方用居室の普請でした。14歳はいくら何でも青年と言うよりは、まだ子供に近い年齢ですが、これは清三郎に対する父親としての社会への登竜門のテストであり、それは、ある程度の勝算が見込める試験だと読んでいたのです。
一瞬、緊張の戦慄が全身を突き抜けた清三郎でしたが、生来の負けん気に火が付き、数日を費やして 図面を引き、仕様書の制作にこぎ着けます。勿論、その間には職人達を集め、石材や木材の相場を見積もるなど、詳細な打ち合わせを繰り返した事は言うまでもありません。
入札用に算出された清三郎の見積もり総額は三千四百両。現代の相場で、最低でも3億4000万円の見積額という事になります。嘉兵衛は臆することなく、手を一切加えないで鍋島藩に書類を提出しました。
結果は、、入札の一番札を引き当てたわけですが、二番札は、なんと僅か百両違いの三千五百両という驚きの結果で、嘉兵衛はこの時の事を終生大きな喜びとして、事あるごとに語っていました。
「清三郎は江戸一番の請負師として頭角を表すことだろう」
「こうなれば、私はいつ死んでも構わぬ。安心して死ねる」
これまで、一切、褒めることのなかった嘉兵衛が、そこまで言い切った訳ですから、それはそれは嬉しかったに違いまりません。
キッチリと鍋島藩奥御殿の普請を終えた嘉兵衛と清三郎の父子鷹に、今度は例の南部藩の国元からとんでもない依頼が舞い込むのはこの3年後のことで、清三郎が17歳の時でした。この事業がキッカケとなって、近代の「日鉄釜石」になろうとは、まだ誰も想像ができない偉業ですが、何に対しても前向きに挑戦する父子の姿勢には、一切、ブレるものがありませんでした。その詳細は次号にて、。(続く、、)
Tommy T. Ishiyama